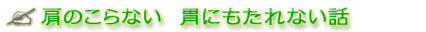 |
||
| PART127 「のんきな殿様とその女房79」>>>「人間界の忌忌しい現象」 | ||
|
著者 小山清春
|
||
| 三回忌にもなると、三途の川をわたってから長いこと旅してきた成就感(なしとげ た喜び)で亡者たちは浮かれごころ、男の子には前世の惻隠の情(いたわしく哀れ む)という言葉もうすくなり、次の世への望みがふくらむ。 「これ、ぼうや、ここまでよくがんばってきたね、お浄土はまもなくだからね。も うお母さんを恨まずともよいぞ」 母親は、わが子を手にかけた罪で実刑10年、宇都宮女子刑務所に収監された。 初めてわが子を抱いたときの胸の感触がぬくもってきて、獄窓に浮かぶあどけない わが子の顔にふっと手を差し伸べては涙する。悔悛の情あつく、模範囚としてひた すらわが子への追善供養の毎日であった。 五道転輪王さまの温かい御言葉はつづく。 「ぼうやよ、人道の鳥居をくぐって、もう一度人生をやり直すがいい。北秋田にい るじいとばあは、あなたが生まれ変わってくる姿を心待ちにしているぞ」 「じいとばあに逢えるの?」 「そうだよ、来世に往ったら思いっきり甘えるがいいよ。こんどこそ幸せになりな さいね。むすめ御と色白のおねえさんもこの後すぐに行くからね、出口のところで ゆっくり待つがよい」 「ハイ…」 男の子には、すでに三途の川をわたって冥界入りしたころのようないじけた面影 はなく、明るく澄んだ瞳で人道の鳥居をくぐった。 昨今の人間界では、少子化の一方で高齢化がすすみ大きな悩みとなっている。 そのような事情にありながら、男の子のように悲惨な死を遂げた子どもの亡者たち がとみに多くなった。わが子を殺し独りあの世へ向かわせるのはしのびないと、お 隣の男の子の首を細い2本のヒモでしめ、道づれにする母親、信じ切ってあずけた 塾の先生に殺された子供、マンションの15階から子供を突き落として悦びを感ず る大人、学校帰りの子供を連れ去り死体遺棄するなど、若い命が容易にうばわれて 実に忌忌しい現象となっている。 冥界から純真な心で生まれ変わっていった子どもたちに、大人を信ずるな、他所 の人は怖い者と教え込まなければならない人間社会の風潮はなんとしたものか、十 王たちは嘆きに余るところである。 そうした少子化と高齢化がすすむ社会をいかにするか、閻魔王のところで開かれ る定例の十王会議においても、これらの命の尊さと大往生について、どのように導 くかが最重要な課題となっている。 冥界に次々と送り込まれてくる亡者の言動をゆるやかに物見高く観ていると、人 間界の現状がよく分かる。さらに浄玻璃の鏡で前世での生活を視ると、個々人の喜 怒哀楽の様子をよく知ることができる。 しかも最近では、高齢化の中で親を看る子どもたちも少なくなり、体調をくずし ても医者にばかり診てもらうわけにはいかないらしく、自らの健康管理が盛んに行 われている。中でもウォ−キングが最適で、遠望する山々の新緑や他所さまの庭に 咲くライラックの香りをぬすみ嗅ぎしながら、歩くことに生きがいを見出したりし ている。 ところが、しっかりと健康管理したばかりに長生きしてしまい、あの世からなか なかお迎えが来ないと嘆く人もいるという。 (著者であるのんきな殿様としては、読者のみなさんが読みやすいようにと、なる べく平仮名で表現しようと思いますが、著者の意図するところを汲み取ってもらう ために、あえて漢字を駆使する場合があります。たとえば“みる”という漢字でも、 それぞれ意味が異なるから…) 「次は一六六一六三八おんな、審理の席へ、」 |