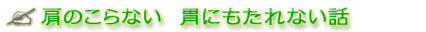 |
||
| PART133 「のんきな殿様とその女房85」>>>「冥界の閻魔(エンマ)さま51」 | ||
|
著者 小山清春
|
||
| 「あなた達も一緒でいいわね」 「おねえさんが、もう少し用事があるんだって、だから、ここで待つことにしたの」 「坊や、おねえさんや娘さんと旅ができて淋しくないでしょう?」 「うん、いつも遊べるから、これをもらったし…」 と、男の子はお土産のマジレンジャーを得意になって見せびらかしている。 この辺りまでくると、「極楽の西風」のさわやかな心地よい風が吹く。この風は お浄土からの余風で、亡者たちはこの風に当たると、十万億土への旅の果てが見え てきて心がやすらぎ、前世の懐旧談などに花が咲く。 「ご主人と会えてよかったですね、夫婦で冥途の旅ができるなんていいことと思わ なければね。だって、前世では生まれてくるのも死ぬのも別々なのよ、ほとんどの 亡者たちは別々の旅でしょう?」 「そうね、亭主といっしょに旅ができるのも、何かの因果なんだね。いまさら殺さ れてきたことを悔やんでばかりいても仕方ないものね。怨みはらしに戻ってきて気 も晴れたし、もう悔いは残らないわ。成仏しなければ…」 「私なんか、二世まで契り一緒に旅しようって約束までしてたのよ、それでも共に 来れなかったもの」 「…でも、亭主にはずいぶん泣かされたわ。三五日の閻魔さまのところで、亭主の 女狂いに困った話を思い切って申し出てみたの。 そうしたらね、浄玻璃の鏡をじっと観なさいって言われたの。 王のそば仕えが、画面にむかってマウスのようなものをいじり、亭主のところの アイコンをクリックしたのね、そうしたら亭主の生前の行動が映し出されたのよ、 しかも鮮やかに、それにはびっくりした。 しかしね、女にうつつを抜かすようなきわどい行動はあっても、凸凹が密着する ような裏切り行為は、どうしても出てこないのよ。だからわたし言ってやったの、 あの人の都合悪いところはみんな削除したんでしょう?って。そうしたら王のそば 仕えは、向きになって言うのよ、そんな事はない!って。 閻魔さまはおもむろに言われたわ、"女房の妬くほど亭主もてもせず"だから安心 しなさい。その一言で気が楽になり、冥途にまで来て初めて亭主の真の善さを知っ たというわけよ。それから愛しくなって、先を行く亭主を追いかけたと言うわけね。 「浄玻璃の鏡って、そんなこともできるんだ。冥界も少しずつIT革命に翻弄 (手 だまにとること)されてきたんだね。…私もあのひとのことを観たいと思うけど、 でも駄目よね、まだ前世にとどまったままだから」 主人と再会できた年かさの女は、女房の妬くほど亭主もてもせず、の言葉を繰り 返し味わいながら、おだやかな気持の旅となった。 さらに、一周忌の審判がすぎたところで、王のそば仕えから、人間に生まれ変わ ってゆくための説法を施されたと言う。 そのそば仕えというのは、秋田県出身の有名な女流作家で、俗名は渡辺喜恵子、 第41回『馬渕川』で直木賞を受賞している。あかぬけして人情の裏表に通じ、し かもしっとりしたお色気があるなかなか粋な感じがした。 初七日の秦広王や三七日の宋帝王にお叱りを受けそうだが、と前置きしてこんな 話をされたのよ。 『人間は老境に入ってから、2、3の秘密があってもよい。それを暴こうとする のは、やじ馬根性だと思っている。このような心境になったのは、ある先生方に 一夫一婦主義を話したところ一蹴されたのがきっかけ。それから性の本質を見つ めるようになったのです……(秋北新聞・1998.8.31から)。 私が同人誌「三田文学」での執筆活動をするようになったころ、谷崎先生(潤 一郎)とご一緒し、私が昭和34年『馬渕川』で直木賞をいただいた翌々年、『 瘋癲老人日記』を執筆されましたが、この本には大変感動しましたのよ。 その中で、77歳の主人公は息子の嫁・颯子の肉感的な魅力に惹かれ、その足 をひたすらなめる姿はなまなましく、己の墓のお骨の上に颯子の足型を乗せよう と考えるが、実行するところで終焉をむかえた……。 老人にも性的欲求があることを世に知らしめた世界でも類がない作品なのです。 また有名な大岡越前守は、年老いた母親に「女はいつまで男を欲しがるもので すか?」と尋ねた。 母親は黙って火鉢の灰を掻きまわしていたという。 そこで「ははぁ、女は灰になるまでか」と悟ったという。 老境に入って、男でも女は灰のなるまでもとなると、老いてますます盛んとい う言葉があり、人間に転生したならば夢と希望いっぱいの人生をおくるがよい』。 (つづく) |