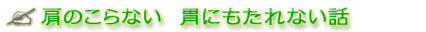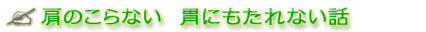我が家に近代農業の機械化ともいうべき『オート三輪車』がきた。
当時、田んぼが1町3反歩(3,900坪)、畑6反5畝歩(1,950坪)、屋敷が320坪
であった。一見すごいなぁ!と思うが、この辺りでは標準面積の農家である。
この程度の田畑を耕作するとなると専業農家でなければできない。
春から秋遅くまで収穫する作物を家まで運び、捌(さば)くには大変な労力を要した。
のんきな殿様ご幼少のみぎり、自給作物は背負って運び、売りに出す物は大八車であっ
た。田んぼは作場道であったから砂利と泥、雨でも降りようものならたちまち泥(ぬ)か
る道になる。
そこへゴムタイヤのリヤ・カーが来たのが小学3年の昭和23年である。親父が先棒
をとり子供たちが後押しする。これによって運ぶ物はずいぶん楽になったものである。
この頃、ほとんどの生計が供出米に頼っていた。親父たちは農業普及員や化学肥料店
などの後押しもあって、試行錯誤を繰り返しながら増収に力を出した。反あたり9〜1
0俵ほどまでこぎつけ、供出米は100俵に。
それでも次第に農機具購入代金がかさむようになり、いきおい農機具店と仲良くなっ
てゆくのである。
畑からの作物はリンゴ・梨・桃・柿などの果実類。これは生計の足しにもならないわ
ずかな物であった。
それでもまだお蚕(ご)さまのよる収入は大きかった。昭和30年代になると、世界的
に新たに化繊が出回ってくるようになり、桑畑が徐々に減っていった。
百姓たちの底力はつづく。桑畑は蔬菜(そさい)畑に代わり、白菜・青菜・キュウリ・ナ
ス・トマトなどの栽培が盛んになってゆく。
この頃、米ばかりではなく、畑の作物も増産するようになり、リヤ・カーだけでは追
いつかなくなった。
やがて、のんきな殿様が高校を出て百姓に専念するようになってまもなくの頃、ある
日、突然ともいうべき、ドウドウ…と唸りを立てて、小屋の前にオート三輪車がご入来。
「くろがね号」という570CCの2気筒エンジン。それまでは産業用車両であると思
われていたのが、農家にも入って来たのである。もちろん中古車両で25万もした。当
時としては破格の値段である。
彼女もつくれず出来もせず、夜な夜なバーへ通い、酒の呑気な馬鹿殿さまだったから、
親父はどんな思いでお金を工面したのか、親の苦労を知る由もない。
いささか百姓生活に嫌気をさし始めていた矢先のことであった。地域にオート三輪車
を持つ家などまったくなかったから、たちまち有頂天になった。
運転には免許証が必要となり、本格的な教習所もなかった頃であったから、自前で運
転技術をマスターし試験を受けた。
ようやく手にしたのが昭和33年3月14日付け。あれから50年。しかも無事故、
何回か優良運転者として表彰を受けたこともある。若気の至りでスピード違反をおこし
たこともあったが、現在はゴールド免許をもらっている。
このオート三輪車が来たことで、蔬菜の栽培に一段と活気を呼び込んだ。
(つづく) |