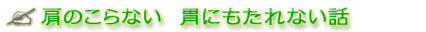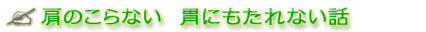雲の中へすっと消えて行った機影を涙霞で見送ったおちかは、清人がもう二
度と母親のもとへ戻ってこないのではないかと不安にかられた。気丈夫なおち
かだが、息子が軍人を志願して飛行機乗りになったときから覚悟の上とは言え、
母の慈愛の涙は止めどもなくながれた。
「お母(か)さ、兄さは休暇をもらうとまた帰ってくるよ」
「んだね……」とは言ってみたものの、心はかるくならなかった。
おちかと敏男は青田への乗合バスで家にもどって行った。
庄蔵とおあきは、お客さまの安吉と彦一を山形県が代表する名刹・山寺へ案
内することになり仙山線でむかった。
駅前の食堂で遅い昼食をとったあと、いよいよ駅から10分ほど歩いて急な
石段をのぼりきると、立石寺・根本中堂がある。
四季をつうじて信仰する参拝客は多い。中に出征兵士の武運長久を祈願する
身内だけの姿も何組か見うけられた。
「おあき、山寺のことを少し説明したらいいんでないかえ?、おまえ、学校で
習ったべさ」
「そんなに詳しくはないけど」
おあきは前導しながら、時折立ち止まっては、
「ここ立石寺は貞観2年というから、今からおおよそ千年以上も前になるけど、
慈覚大師、この辺りでは円仁さんというけれどね、その方が開山したといわれ
ている。
ご本尊は木造薬師如来坐像で重要文化財に指定されておりますの。
この根本中堂には、京都の比叡山延暦寺から分燈した千年不滅の法燈が、今
も灯りつづけている」
おあきは教壇生活にも慣れてきたせいか、説明は歯切れがいい。
午前の錬兵場で清人のゼロ戦闘機を見送ったころは暑かったが、ここ山寺の
うっそうとした樹木にかこまれると別世界のしのぎやすさである。
彦一は、おあきが説明するたびに指をのばす、絽(ろ)のきものの袖口からの
ぞく色白な腕のうごきに、大人の色香がなまめかしく感じられた。
「これが奥の細道の旅でおとずれた松尾芭蕉の句碑です」
根本中堂へお参ったあと、左へ折れたところに松尾芭蕉の『閑さや岩にしみ
入る蝉の声』の句碑がたっている。
やがて『開北霊窟』と記された扁額をかかげた山門の前に立った。
ここ山寺は岩のうえにさらに岩を重ねたような巌山となっている。
山の上には5つの寺が点在するように建っている。1015段もある険しい
山道をのぼって、一つ一つの寺を巡りながら奥の院まで登りつめるのである。
「ここは天台宗の教学の道場として開かれたところで、ところどころに大小の
石窟があるでしょう?大きいものは霊窟となっています」
いよいよ門をくぐり登りはじめると、左手に岩間に生えた樹木の間をぬうよ
うに滑り台がはるか中腹から長々と延びてきている。幅が1メートルほどで長
さが300メトールぐらいはある。
ちょうど小学生の一団が歓声をあげてつぎつぎと降っているところだった。
その光景をながめていたおあきは、夏休みに入った受け持ちの子たちのこと
を思い出していた。
「彦一っあん、はやく戻るべはぁ、ねぇ、子どもたちが待っているから」
「んだじゅ、かあちゃんの店さ、あの子たちが、おあき先生はまだ来ねかぁ?
って毎日来ているべさなあ」
「こっちでの法事が済んだら帰ろう」
さらに登ると姥堂があって、傍らに奪衣婆の石像と隣りに地蔵尊が祀られて
いる。
「この奪衣婆は三途の川のほとりで、亡者の着物をはぎとっているのね。その
剥ぎとった衣装は川のほとりの衣領樹にかけられる。枝のしなり具合で前世で
の罪の軽い重いを量るんだそうよ。あぁ、怖い!お顔……、ここを境に上の方
が極楽、下が地獄への分かれ目といわれているのよ」
 |
(つづく)
|