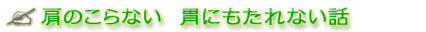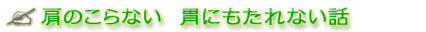近代化をめざす日本は、大正3年、欧州大戦という世界中を巻き込んだ第一
次大戦に参戦。翌年には東京株式市場が大暴落するなど、次第に不況の風がじ
わじわと吹き荒れるようになる。とくに関東や東北地方の田園地帯では凶作が
つづき、人々の暮らしは貧困のどん底にあった。
ひそかに口減らしの風習があり、最も残酷なのは生まれると直ぐに川へ流し
てしまう間引き。川ごみにからまって淀んでは流されながら次第に白骨化して
いき、やがて海の藻くずと化してゆくのである。
ここに登場したのが、貧しさの弱みに付け込んだ女衒(ぜげん)たちである。
さかのぼること江戸時代から娘たちを遊女として遊郭へ売り飛ばす人買いであ
る。
生活が苦しい親は、同じ働くにしてもきれいな着物を着てお客さんと遊ぶ、
あわよくばいい旦那さまに身請けでもされれば玉の輿、大変なご出世で親たち
も鼻が高かった。
それとも毎日泥だらけになって子守りをしながら、草木のろくに熟してもい
ない実などで食いつなぐ生活とどちらがいいか、年頃の娘になると親や家族を
助けるのであればと、自ら遊女に身をしずめることもあった。
女衒はうす汚れた風体の娘でも、華美な着物を着せれば上玉になるものと、
見抜く商売の勘はするどい。初めはにこやかに、次第にきびしい下心をあらわ
にしてゆく。安く買って高く売りたい女衒と、「こんなへな子でも、買ってくれ
るのであれば……」と親たちとのかけ引きの会話つづく。
押したり引いたりの繰り返し。
不憫におもう親の情けも、ついに商売上手な女衒の手に落ちるのである。
「おとぅ、○○(幼い弟)さ、ままいっぱい食わせてけろな」
「話が決まれば早いほうがいい、善はいそげだな」
涙ながら別れを惜しむ家族を尻目に、薄情にも急き立てて行く。
童謡『花いちもんめ』は、そんな悲しい娘売買の様子が子ども達の遊び唄と
なったのである。
「勝ってうれしい……」は、買ってうれしい……、女衒の気持。
「負けてくやしい……」は、値切られて安く売ってしまった親の気持である。
押したり引いたりのかけ引きのあと、ジャンケンするのは話がきまった意味
である。
匁は一両小判の60分の1の値段。あるいは遊郭で売られた娼婦の花代とも
言われている。この唄の発祥の地は栃木県の田園地帯であった。
(参照・会田道人著『童謡の謎』)
おあきの教え子の中にも、何人かの叔母たちが女衒の手にかかった。
しかし、このことに子どもたちや親たちの口元がほころびることはなかった
が、“人の口に戸を立てられぬ”もので、噂がひっそりと広まるものであった。
ヨザエモンの叔母は14歳の秋、冷害のあおりをうけた親の元を離れ、泣き
泣き女衒に手を引かれて群馬県の温泉場の遊郭へ。20歳の時に花柳病におか
され、懐かしいふるさとの山や川を見ることもなく、親兄弟の顔を見ることも
なく、蒸し暑い日の夕刻、別棟の戸口から桶棺でひっそりと運び出され葬られ
たのである。
サツコの叔母は、22歳の春に、千葉県の醤油醸造元の次男坊に見初められ、
嫁いでいった。
大正12年には関東大震災が襲う。
不穏な社会情勢の中で、昭和12年7月7日、盧溝橋事件をきっかけに日本
の中国侵略ともいうべく「日中戦争」が勃発した。しかし日本側は、これは戦
争ではないとかたくなに否定し、「支那事変」であると呼称したのである。
やがて、これが長期戦化の様相呈してきた。
(つづく)
|