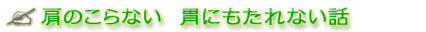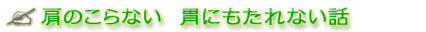彦一は、馴染みの遊女へ入れ揚げてはみたが情欲のはけ口にすぎず、おあき
への恋慕の情が深まることはあっても、断ち切ることができなかった。
一方、おあきにとっていくら下宿人とは言え、彦一と同じ屋根の下で家族同
然の暮らしが一年以上をすぎていた。しかし彦一への男女の情愛が湧くことは
なかった。
徴兵検査の時期がせまる。
日本は、日露戦争の勝利に酔いしれて日中戦争が長引く中、後戻りできない
まま、いっそう軍事化がすすんだ。
「兵隊検査で甲種合格してよ、日本男子の本懐を遂げるんださげの、そんでえ
えなだぞ」と、まわりの人たちは異口同音に煽動する。
おあきは人間として命あってのことと思えば、居たたまれない気持であった。
受け持ちの男の子たちが、幼い弟や妹を背にくくりつけて桑畑の中をくぐり、
土手のかや藪に身をひそめたり、河原におりて腹ばいになって、鉄砲にみたて
た幹の枝を手に「兵隊ごっこ」の遊びに明け暮れていた。女の子となると、負
傷のまねをした男の子の腕を、手ぬぐいの切りはしでしばる介護の真似をした
りする。
おあきは、そんな子供たちが不憫でならなかった。
直ぐにでも子どもらの遊びのところへ走っていって止めさせたい気持ちを、
心の底にぐっと押しこめ、教師としての顔で接するほかなかった。
「まま(飯)いっぱい食って大きくなれよ、立派な大人になるんだぞ」と、大
人たちは言い聞かせる。やがて兵隊となり死ぬことが本懐だとは、人間として
何と理不尽なことか。
女には女としての使命があり、「産めよ殖やせよ」の時代である。
この頃、「妊産婦手帳」の妊産婦ノ心得欄の第一条には、「丈夫ナ子ハ丈夫ナ
母カラ生レマス。妊娠中ノ養生ニ心ガケテ、立派ナ子ヲ生ミ国ニツクシマセウ。」
とあり、丈夫な体に心がけ、すこやかな子どもをたくさん産むことが、何より
もお国のためであると明記されている。
さらに食事のとり方、さわりに注意して毎月一回の受診、衛生綿、セッケン、
木炭、砂糖の配給や乳加配衣料切符交付など、こと細かなこころ配りがある。
お国のために軍務につくのは、飛行機乗りの兄清人ひとりでいい。その兄も
去年の夏、山形の錬兵場へ飛来し霞ヶ浦の航空隊へ帰還していったあと、どの
辺の空を飛んでいるのかわからないまま、ただ元気に軍務に励んでいる、との
便りだけであった。
6月に入ったある日、父庄蔵からの便りがきた。
便箋に達筆な文面で、娘の安否と兄清人が「ご両親様、今は鹿児島の鹿屋に
おります」と一言だけのハガキがきた、という内容である。
(つづく)
|