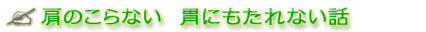 |
||
| PART73 「のんきな殿様とその女房25」>>>「梅干しの唄」(1) | ||
|
著者 小山清春
|
||
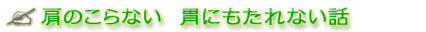 |
||
| PART73 「のんきな殿様とその女房25」>>>「梅干しの唄」(1) | ||
|
著者 小山清春
|
||
| 『お隣の国から使者がやってきた。「このたびは、こういう問題を持ってきた。 |
| 先日、カルチャークラブのある方から、91歳のおばあさんが歌う『梅干しの 唄』のテープを聞かせてもらった。「戦友」(明治37年)の節回しを巧みに操 り、矍鑠(かくしゃく)とした声。節まわしや文句の情感からすると、日露戦争 当時の唄ではないかと思われる。 「私の母ですの」という娘さんの面影から若い時分を思い描くと、色白丸ぽちゃ でさぞかし持てたことだろうと思う。 |
 『梅干しの唄』の宇野千代さん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 梅干しの唄 (節は『戦友』から・明るくは『鉄道唱歌』で) 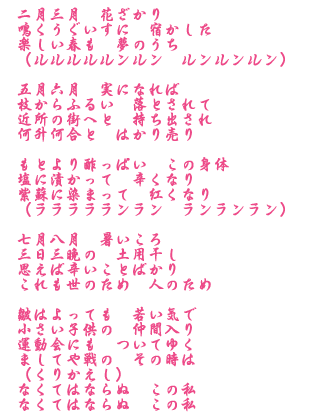 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| おばあちゃんが生まれた大正元年は、尋常小学校唱歌「茶摘・汽車・村祭・春 の小川・村の鍛冶屋」などが歌い出された。タイタニック号が氷山に衝突したの もこの年。東京州崎遊郭で大火、折りからの風にあおられ、1,150戸が焼失。 あられもない姿で右往左往する遊女や客を、壮観だなぁと眺める野次馬がきっと いたと思う。いつの世にも他人の不幸を喜ぶ、暢気な馬鹿や野次馬がいるものだ。 |
|
(1)の了 |