![]()
|
|
|
|
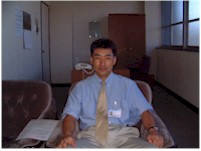 |
安藤電気株式会社
|
| はじめに・・・・・・ お忙しい中、ご協力いただきまして、本当にありがとうございました。 この場をおかりしまして、心より御礼申し上げます。 |
| アルターシステム㈱ 松 永 |
|
文中敬称略 |
| Q まず会社の概要を簡単にお願いします。 |
| 大石) 2つの事業本部体制で、一つは主に計測機器と通信ネットワーク機器を扱っている通信事業本部と、 2つ目はATE製品を扱っているATE事業本部からなっています。 計測機器分野としては、ディジタル通信、光、移動体通信用計測器、などを、通信ネットワーク機器分野 では、高速ディジタル専用線電送装置などを扱っています。また、マーキング装置などのFA機器分野の製品も 扱っています。 ATE事業本部では、ロジック、メモリ用のVLSIテスタ、テストバーンインテスタ、リニア/DCテスタ、 やオートハンドラを扱っています。 |
| Q 実際に生産拠点は国内がメインですか? 海外のほうはいかがですか? |
| 大石) 6カ国に海外拠点はありますが、生産は国内だけです。 海外はサービス関係が主体になります。 |
| Q 現在の従業員数はどれくらいいらっしゃるんでしょうか? |
| 大石) 1000名強というところですね。 |
| Q 通信とATEとどちらが好調ですか? |
| 大石) 通信とATEでは通信の方が好調ですね。 |
| Q それで、本社は今年8月に蒲田から川崎に移転されましたよね、事業所は何拠点あるのですか? |
| 大石) そうです、8月に蒲田から川崎へ本社事務所として移転しました。
本社事務所には両事業本部があります。 事業場は静岡県の浜北市と湖西市にあります。浜北事業場がATE関連、湖西事業場が通信関連と なっています。 |
| Q 大石様の技術管理部の業務内容をお聞かせ願いますか? |
| 大石) 私のところは、全社のEDAシステムの導入から構築、あと運用まで含めてサポートをしています。 システム構築といってもツールの評価、導入だけではなく、当社の設計に合わせたカスタマイズのための プログラム開発と、単にシステムを提供するだけではなく、我々が導入したツールを活用し設計者と一緒に なって設計を進めるような設計支援を行っています。ここでいうEDAのシステムとはASIC,FPGA用の HDL設計環境とプリント基板用の回路設計環境の両方をサポートしています。 |
 |
| Q メカは違う部署ですか? |
| 大石) えぇ、違う部署ですね。 共通的な部分を担当している部署はありますがどちらかというとメインがもう事業部なんですよ。 プリント基板設計についても別の部署でやっていたのですが1年前から私のところと同じグループになり 一緒に活動しています。 |
| Q 上流から基板設計までですか? では電気はもう、ほとんどサポートされているといった感じですね? |
| 大石) そうですね、設計環境自体が上流から下流まで統合されてきていますので、サポート部門もバラバラより 統合されていた方がやりやすい面が多いですね。 |
| Q 上流の方のツールなどもお聞きしたいんですが、上流のASIC,FPGAでのLSI設計ではどのツールを 使用されているんですか? |
| 大石) シミュレータや解析ツールなどいろいろなメーカのツールを使用していますが合成関連はsynopsysのツールを 使っています。 あとは、NEC、ザイリンクス・アルテラなど各ベンダーのデザインキットを使っています。 |
| Q FPGAなどを使われる需要も結構多いんでしょうか? |
| 大石) 今、社内はFPGAとかPLDのほう多いですね。一昔前はゲートアレイが主だったんですけど、やはり最近は 短納期要求や利便性から、設計者はFPGAとかPLDの方を好んで使います。割合は9:1くらいですね。 |
| Q そのあたりの設計などは内部で行なわれるケースが多いんでしょうか? |
| 大石) 社内ですね。 協力会社の方が社内に入って一緒にやることはありますけど、設計を外の会社に全部 お願いするということはあまりないですね。 |
| Q そうしますと回路設計からプリント板設計という流れでは、どういったツールを使われているのでしょうか? |
| 大石) システムの移行にはデータの移行は避けて通れない問題です。最初はライブラリーと回路図のデータを含めて、 プログラムでトランスレートしようとトライしてみましたが結局手直しが入り上手くいかなくて、今はライブラリーは 仕様の見直しを含め全部新規で作成し直す事に決めました。いずれにしても機能が増えるシステムに対し そのままの古いライブラリでは情報が足りませんから。回路図についても同じです。既存の回路図を流用しようと すればトレースするしかありません。回路図はプリント基板ごとに作成されているので装置回路図としてみた 場合には新旧の回路図が混在できますが、プリント基板ごとに考えると社内でやるのか協力会社にお願い するのか全部入れ直すしかないですね。 |
 |
 |
| Q 全面移行するということですか? |
| 大石) はい、移行していきます。しかし、完全に旧システムがなくなるまでには時間が必要と考えていますが。 今は新規性の高く、流用度の低いのものから適応を開始しています。従来の回路の手直しとか、 パターン設計の部分を少し改版するような場合は、全てやり直すということは大変なので、そういう場合は 従来のシステムでやるようにしています。やっぱり納期優先で設計が動いていますから、システムを変えたから 納期が延びるといっても許してくれませんからね。 |
| Q やはり、ライブラリーがいちばん大変ですよね。みなさん、そこでご苦労されていると、よく聞きます。 |
| 大石) 我々も、CADのシンボルを作る仕様というものがありドキュメント化されていますが、現在の運用や仕様に 合っていないという問題があり、今回システム移行に伴い、アルターシステムさんに協力してもらって、仕様の 見直しを行っています。高密度化ということと逆の動きになってしまいますが、現在はシンボルの共通化 ということも協力をお願いして進めてもらっています。 |
| Q 部品の数を減らすということですよね。実際に通信機器、ネットワーク機器も含めてなんですけど、意外とクロックが 早い設計も多いと思いますが、その中で、シミュレーションの対応は、いかがですか? |
| 大石) はい、一部ではやっています。この検証・解析といったところがシステム移行の目的でもありますので、 これから重点的にやっていかなくてはならない事です。 |
| Q そういったわけで、ベースをしっかりしていこうということですね。では次に、最近、電気設計をしている時に3次元的に メカとのぶつかりですとか、干渉という部分で、電気のCADデータの一部をメカCADに、といった連携のニーズは、 いかがですか? |
| 大石) とくに高さですよね、そのような問題も起きています。設計部門からは、実際に基板を作って装置に入れると、 蓋が閉まらないなどといったことが起きています。ですから、そのようなことも含めてシミュレーションができない ものかという要望も出ています。今、高さの情報については、部品情報として扱うように考えています。 |
| Q 先ほど、大石さんが共有化のことをお話してくださいましたが、最近、部品の品種を少なくしていこうという動きが 多いように思います。設計の方は、新規部品の採用をしていくと思いますが、部品が増えていきますよね、 その取り組みはいかがでしょうか? |
| 大石) はい、やはり当社の場合も部品がどんどん増えています。同じような部品でも社内に在庫が貯まっていくという 問題があったので、数年前に社内でプロジェクトを起こしました。「部品情報システム」という、ひとつの部品情報の データベースを構築したんです。ですから今、新規部品を使うためには、そこに申請して登録しないと使えないように なっています。その情報の中では在庫管理もされているので、設計者はそれを見て選び、設計者は申請し登録 されないと使用できないので、ある程度、絞り込めていると思います。 |
| Q そこがフィルターの役割をしているわけですね。 |
| 大石) はい、社内の仕組みとしては、設計者全員が共通で部品情報システムを活用しています。 |
| Q 最後に、今期の最大のテーマをお聞きしたいのですが? |
| 大石) そうですね、やはり私のグループは、今年度、新しいシステムへの移行ということが最大のテーマです。 先ほども言いましたように、その先で狙っているのは検証・解析といったところに集中していかなくてはならないので、 その下地作りをしているところですね。その移行作業が今期のテーマで、来期に関してはその検証・解析に トライしていきます、しかし支援部門だけではうまくいきませんので設計部門と一緒に進めていくことになると 思います。 |
|
お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。
|